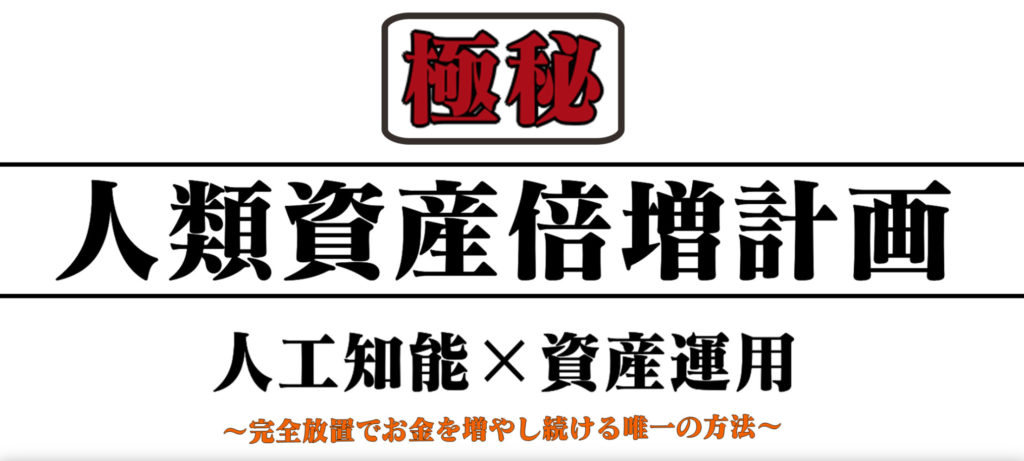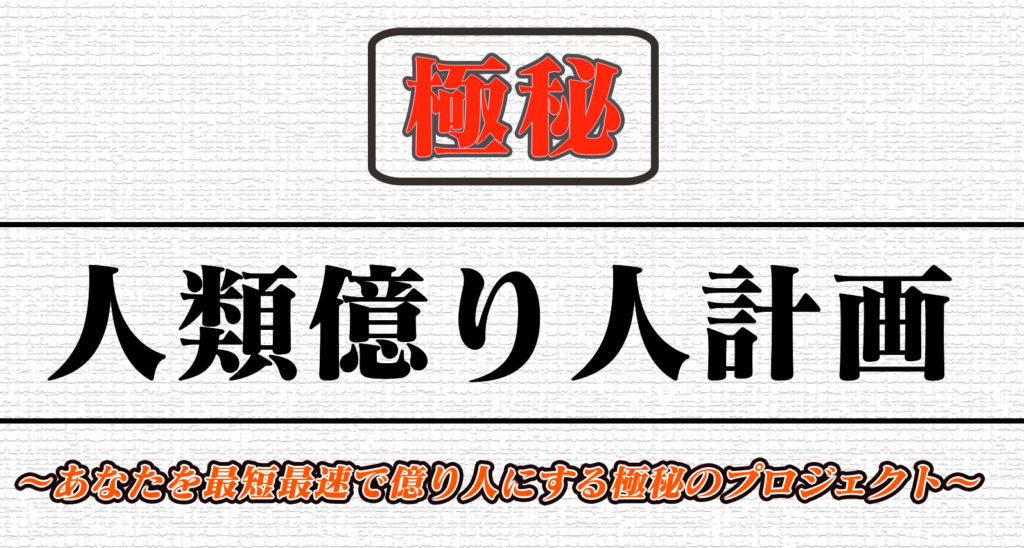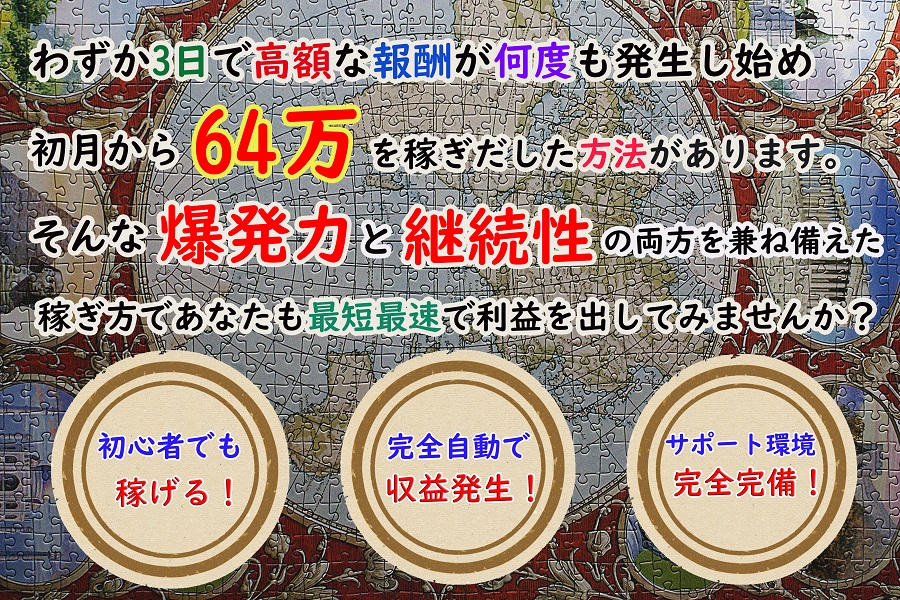当ページを読んで分かること
- ドルコスト平均法の基礎知識
- ドルコスト平均法の注意点
- ドルコスト平均法をFXで活用した事例
株式の積立て投資に用いられるイメージの強いドルコスト平均法ですが、FX投資においても効果を発揮します。
今回はドルコスト平均法とはどんな手法なのか、さらには使用するときの注意点をチェックしておこうと思います。
ドルコスト平均法とは?

ドルコスト平均法とは、定期的に一定金額の通貨を購入し続けるトレード手法のことをいいます。
言葉では分かりにくいと思うので、チャートでイメージしてみてください。

理解するポイントは、毎回同じ金額を購入するということです。(同じ枚数ではありません)
そのため、レートが高いときは枚数が少なく、レートが低いときは枚数が多くなります。
枚数によって購入金額を調整していると理解することもできますね。
定量購入とドルコスト平均法(定額購入)の違いは?
定期的に購入するとき、よく行われるのが枚数を固定するという方法です。
1枚と決めていれば、そのときのレートに関係なく毎回1枚の購入を行います。この購入方法は定量購入と呼ばれています。
さて、この定量購入とドルコスト平均法(定額購入)で、平均購入単価にどのような違いがあるのでしょうか?
以下のようなルールでそれぞれ定期的に購入することを考えてみます。
・定量購入→1枚
・定額購入→100円
5週間にわたって毎週、定期的に株式を購入するとしましょう。
| 購入方法 | 週と価格 | 1週間目
100円 |
2週間目
70円 |
3週間目
60円 |
4週間目
90円 |
5週間目
130円 |
合計 | 平均購入金額 |
| 定量購入 | 投資金額と枚数 | 100円
1口 |
70円
1口 |
60円
1口 |
90円
1口 |
130円
1枚 |
450円
5枚 |
90円 |
| 定額購入 | 投資金額と枚数 | 100円
1枚 |
100円
1.43枚 |
100円
1.67枚 |
100円
1.11枚 |
100円
0.77枚 |
500円
5.98枚 |
83.61円 |
表の中で注目してほしいのが、平均購入金額です。
定量購入よりもドル平均法(定額購入)による購入の方が下回っていることがわかります。
購入金額を一定にするドル平均法では、価格が下がった時に購入する数量が多くなり、価格が上がったときに購入する数量が少なくなるので、その分平均購入金額が下がります。
どんな条件下であっても、ドル平均法による購入(定額購入)の平均購入金額が、定量購入の平均購入金額を上回ることはありません。
平均取得単価などとも呼ばれますが、この数字が低いということは、より安い価格で取得した買いポジションを保有することを意味します。
より大きなリターンを生み出すパワーを持っているとも言えるでしょう。
ドルコスト平均法の注意点
ドルコスト平均法にも苦手なことがあります。注意点をチェックしておくことで、より良いトレードができるようになるはずです。
注意点1|下落相場では含み損が拡大していく
ドルコスト平均法で最も注意しなくてはならない点は下落相場で含み損が拡大していくということです。
エントリーと反対方向のトレンドが発生した場合、含み損がどんどん増えていき、損切りしなければ悲惨な結果になってしまいかねません。
いくら価格が下がったところでたくさん買ったとしても、価格が下がり続けたら利益を出せるはずがありません。
ドルコスト平均法は、下落相場でないことが絶対条件の手法と考えておいてくださいね。
注意点2|手数料がかかる
ドルコスト平均法のように何度かに分けてトレードを行う場合、一度に購入するよりも手数料が嵩んでしまう傾向にあります。
少しでも手数料負担を小さくするため、なるべく売買手数料の安いFXブローカーを使用するようにしましょう。
注意点3|スワップポイントに注意
金利差によるスワップポイントにも注意が必要です。
スワップの支払い額が大きい通貨を購入すると、毎日スワップを支払わなければなりません。
数日間かけて積み立てていく場合、高金利通貨建てで低金利通貨のポジションを持つと、まとまった損失が発生していってしまいます。
ドルコスト平均法を実際の相場で試してみよう!
ここまで読んでいただければ、ドルコスト平均法の基本的なことはご理解頂けたかと思います。
FXでドルコスト平均法を試してみたいと思います。
まず押さえておきたいのが相場の流れです。下落相場になる可能性が極めて低い相場でエントリーしましょう。
シミュレーションに使用するチャートは2020年5月~8月のユーロ円の日足です。
この期間、ユーロドル上昇、株高⇒クロス円上昇の流れから、レートの上昇が続いていました。
当時、ファンダメンタルズ的にもテクニカル的にも上昇する可能性が高いと判断できたはずです。
ただし、一辺倒に上昇が続くケースは稀です。
そのため、ドルコスト平均法の考え方にしたがって、相場の調整時に少し多めに購入し、平均取得レートを少しでも下げることが大切と言えるでしょう。
ドルコスト平均法の戦略

上昇トレンドが本格化した6月からトレードを開始すると仮定しましょう。
チャートの丸印が購入ポイントです。
トレードルールを以下のように設定します。
・通貨ペア:ユーロ円
・トレード頻度:(毎週)
・金額: 10万円(1万円×10回)

このときの平均取得単価は以下のように計算することができます。
平均取得単価=100,000円÷822.7979=1ユーロ121.5365円
定量購入の場合、平均取得単価は以下のようになります。
平均取得単価=12156円÷10000=121.56円
今回のケースでは、差はそれほど大きくありませんが、もう少しボラティリティの高い相場では、平均取得単価の差は大きくなります。
一時的に大きな調整のあったポイントでも購入しましたが、枚数を増やすことで平均取得単価を下げ、利益を上げやすい状況を作り出すことができています。
今回の相場では、ある程度の利益を生み出せたことになります。
損切りが必要な場合も
ただし、損切が必要な場合も出てきます。
注意点でも紹介したように下落相場でこの手法を行うとどんどん損失が膨らんでいきます。
そのため、ファンダメンタルズもしくはテクニカルで根拠があれば損切りしましょう。
今回の場合、週足に下降トレンドラインを引き、ラインを下に割ってきたら、仕方なく損切りを行わなければいけません。

※週足で、四角で囲んだ場所がシミュレーションを行ったエリア
ドルコスト平均法まとめ
ドルコスト平均法はFXでも充分通用するトレード手法です。
手堅くロジカルにトレードをしていきたい方はぜひ一度試してみてくださいね。